
離乳食で「喉を詰まらせないか」は、ママパパが常に神経をつかっていることではないでしょうか。気にしすぎるあまり食材を柔らかく小さくしがちで「噛む力」が育たず「丸呑みしがち」になっているケースもあるかと思います。今回は管理栄養士の佐藤翔子さんに“丸呑みしがち”な原因と対策について教えていただきました。
丸呑みしちゃう原因はこれ!

丸呑みは、お子様のお口の機能の発達状況と食材の大きさ・硬さが合っていない場合や、噛む力が十分に育っていない場合に起こりやすいです。
丸呑みになりやすい離乳食スタイル
- ● スプーンに盛りすぎ:一度に口に入れる量が多い。
- ● スプーンを口の奥まで入れる:受け身になり、自分で取り込む動作が育ちにくい。
- ● 食べ物を次々と与える:飲み込む時間を待たずに次の一口を与えてしまう。
- ● 早食い:口に入れたものを急いで飲み込む。
- ● 水分で流しがち:食べ物を水やお茶で飲み込む。
食べ物の形態に応じて噛んだり、つぶしたりする動作は、自然に身につくわけではありません。必要性がなければ発達しないため、発達に合わせた離乳食や与え方が重要です。

噛む力の重要性

食べ物をしっかり噛むことで、口周りや頬の筋肉が鍛えられ、窒息のリスクを軽減するだけでなく、満腹感を感じやすくなり、食べ過ぎや肥満を防ぐことができます。また、噛むことで唾液の分泌が増え、食べ物の消化吸収がスムーズに進みます。
例えば、早食いや食べ物を水分で流し込む、一度に多くの食べ物を口に入れる習慣があると、噛む回数が少なくなり、窒息のリスクが高まるとともに、満腹感を感じずに食べ過ぎや肥満に繋がる可能性が高まります。
噛む力は、お子様が食事を安全に楽しみ、成長するためだけでなく、食習慣を形成するためにも欠かせない力です。
離乳食時期別×丸呑み対策
初期、中期、後期、完了期に共通していえることとして、「しっかり噛める姿勢をつくる」ことと、「お子様の口の動きや発達度合いに合わせた食材の固さや大きさ」にすることは基本です。
詳しくはこちら ↓
「離乳食を食べない」を卒業!月齢別に解決!管理栄養士が教える食べない原因と姿勢のコツ
月齢別の口や食べ方の発達の目安

離乳食初期(5~6ヶ月ごろ)
舌が前後にしか動きません。
離乳食のスプーンの与え方で唇や舌を鍛えることができます。
スプーンでの与え方のポイント
- 1. スプーンで軽く下唇に触れる
スプーンで下唇に軽く触れて、「これから食べ物が来るよ」とサインを送ります。 - 2. スプーンを水平に置く
口を開けたら、スプーンを水平に下唇の上に置きます。 - 3. 上唇で取り込むのを確認する
上唇が自然に下がり、食べ物を取り込もうとする動きを待ちます。 - 4. スプーンをゆっくり引き抜く
スプーンを上唇にこすりつけたり、口の奥に入れすぎないよう注意してください。

この頃は飲み込む際に、下唇を内側に巻き込む動き(下唇の内転)が見られます。
これは、口唇の力がまだ十分ではないため、舌を上顎の前のほうに押しつけやすくするための自然な動きです。この下唇の内転は、大人が自然に行う飲み込み方(成人嚥下)を身につけるための重要なプロセスです。口唇の力が少しずつついてくると、上下の唇をしっかり閉じて飲み込むことができるようになります。

離乳食中期(7~8ヶ月ごろ)
舌が前後に加えて上下にも動くようになるため、少し粒感のあるものや舌で押しつぶせる食材を取り入れていきます。スプーンでの与え方は初期と同じですが、この時期では以下の変化が見られます。
- 食べ物を舌で上あごに押しつけてつぶす。
- 数秒間「モグモグ」と口を動かしゴックンと飲み込む。

離乳食後期(9~11ヶ月ごろ)
舌が前後・上下だけでなく左右にも動くようになるため、舌でつぶせない食べ物を左右に寄せ、歯ぐきでつぶして食べることが出来るようになります。
つかみ食べで自分で食材を取り、一口の量を学んだり、食べ物をかじり取る練習をしていきましょう。

離乳食完了期(12~18ヶ月ごろ)
舌が自由自在に動き、歯ぐきで噛めるようになります。
手づかみ食べの動作がスムーズになりますが、かじり取りや一口量の調整がまだ不十分なことがあります。見守りながら声掛けをしてサポートしてあげましょう。

手づかみ食べを積極的に取り入れよう
手づかみ食べは、自分で食べ物を持つことで、食材の大きさや固さを手で感じ取り、無理なく口に入れられる量を学べます。また、前歯でかじり取る経験を重ねることで、一口量を自然と調整できるようになります。この過程で、食べ物を口の中で動かし、噛みつぶす力も発達し、丸呑みを防ぐ基盤が育まれます。
かじり取りの練習方法
お子様が握りやすく、前歯で噛み切りやすい固さの食材を用意することから始めます。スティック状の野菜やトーストしたパンなど、ベタベタせず手に持ちやすい食材がおすすめです。
最初は大人が食材を持ちながら、前歯で一口量を調整してかじらせるようにしましょう。慣れてきたら、お子様と一緒に食材を握り、前歯で少しずつかじり取れるように補助してあげてください。
自分でかじれるようになった後も、食材をお口に詰め込むことがあるため、引き続き見守りながらサポートすることが大切です。

手づかみ食べの進め方は以下のコラムも参考ください。
脳も心もぐんぐん育つ!手づかみ食べのすすめ【管理栄養士コラム】
手間をかけずに噛む力がupする工夫
遊びの中でカラダを動かして噛む力を鍛えよう

噛む力は、口周りの筋肉だけでなく、全身の発達とも深く関わっています。特にハイハイは体幹を鍛える動きとして非常に重要です。体幹が安定することで、噛む際の姿勢や力も安定しやすくなります。ハイハイを卒業したお子様でもハイハイの姿勢で遊んでみましょう。また、笛を吹く遊びも口周りの筋肉を鍛える方法としておすすめです。音が出ることが楽しく、お子様も自然と楽しみながら練習できます。
カミカミグッズを使おう

市販のカミカミグッズ(歯がためや噛んで味わうフィーダー)は、遊び感覚で噛む動作を促し、咀嚼力を育む便利なアイテムです。 シリコン製のものは丸ごと洗えて清潔に使え、衛生面でも安心です。
★歯がため
★噛んで味わうフィーダー
まとめ

丸呑みは、噛む力や食べ方の発達過程で見られる自然な行動ですが、そのまま放置すると窒息のリスクや成長に影響を与えることがあります。これを防ぐためには、月齢に合った食材の固さや大きさを選び、つかみ食べやかじり取りを通じて噛む力を育て、一口量を調整する力を身につけさせましょう。また、詰め込みそうなときは声掛けやサポートを行い、安全で楽しい食事環境を整えることが大切です。
筆者紹介
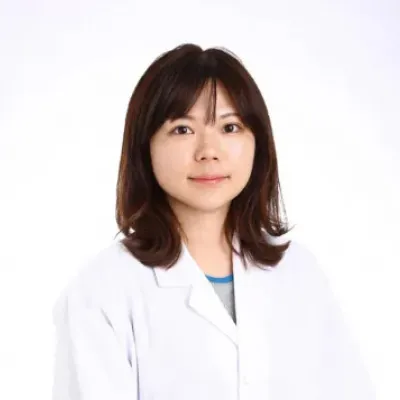
- 佐藤翔子管理栄養士 / フードスペシャリスト
- 思春期に食で悩んだ経験から「食で悩む人を助けたい」と思い管理栄養士になる。病院や保育園での12年間の経験や自身の子育て経験を活かし、現在は食で悩むママを減らすことを目指し活動中。「食べる楽しさや大切さ」を親子で感じてもらえるよう、Instagramを中心に発信する傍ら、コラム執筆や産後ケア事業で栄養相談も行う。














